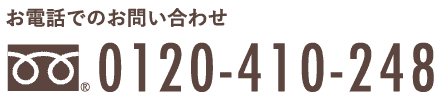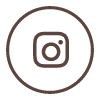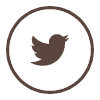2023.03.17
ビタミン不足は食べ物で解消しよう!摂り方のコツも紹介
こんにちは!食と健康をサポートするリセライーツの椿本です。
ビタミンは、人が健康を維持していくうえでとても大切な栄養素。
体内ではほとんど作ることができないため、普段の食事から摂取する必要があります。
そのため、栄養の偏った食事を続けるとビタミン不足になることも。
そこで今回は、ビタミン不足が気になる方におすすめの食べ物をご紹介します!
ビタミンを効率良く摂取する方法やビタミンの働きについても詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

目次
ビタミン不足になるとどうなる?
ビタミン不足になると、どのような症状を引き起こすのでしょうか。
まずはビタミンとはどういう栄養素なのかを解説していきましょう。
ビタミンとは
ビタミンは、5大栄養素(タンパク質・糖質・脂質・ビタミン・ミネラル)の1つで、人が健康を維持していくうえでとても大切な栄養素です。
からだのエネルギー源になるタンパク質、糖質、脂質に対し、ビタミンはそれらの代謝を助ける“潤滑油(じゅんかつゆ)”のような働きをしています。
1日に必要な量はわずかですが、体内ではほとんど作ることができないため、普段の食事から摂取する必要があります。
ビタミンには13種類あり、水溶性ビタミン9種類と脂溶性ビタミン4種類に分けることができます。
水溶性ビタミン
水溶性ビタミンは「ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン(ビタミンB3)、パントテン酸(ビタミンB5)、ビタミンB6、ビタミンB12酸、葉酸、ビオチン」の9種類。
ビタミンC以外はまとめて「ビタミンB群」と呼ばれています。
水溶性ビタミンは水に溶けやすいため、体内に取り込んでも蓄積することができず、過剰に摂取しても尿などから体外へ排出されてしまいます。
そのため、水溶性ビタミンは不足しやすい傾向があり、普段から意識してこまめに補給する必要があります。
また、水溶性ビタミンは加熱などの調理方法によって失われやすいため注意が必要です。
脂溶性ビタミン
脂溶性ビタミンは「ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK」の4種類。
体内ではほとんど合成できないため、食事から摂取する必要があります。
脂質と一緒に摂ると体内へ吸収されやすくなるのが特徴です。
ただし、脂溶性ビタミンは体内に蓄積されやすく、過剰に摂取すると過剰症を引き起こしてしまう可能性も。
普段の食事から摂る量で過剰摂取になることはほとんどありませんが、サプリメントなどから摂取する場合には気をつけましょう。
ビタミン不足になるとどうなる?
極端な偏食や過度に食事を制限するダイエットなどにより、栄養バランスが崩れビタミンが不足した状態が続くと、ビタミン欠乏症(けつぼうしょう)を引き起こす可能性も。
主な病気として、ビタミンB1不足により脚気(かっけ)、ビタミンC不足による壊血病(かいけつびしょう)、ビタミンA不足による夜盲症(やもうしょう)などがあります。
このような病気まではいかないけれど、ビタミンが不足すると、疲れやすい、肌荒れ、体が冷えやすい、肩がこりやすい、口内炎ができるなどの日常的にからだに不調が現れることもあり、このような状態を「潜在的ビタミン欠乏症」といいます。
ビタミン不足解消におすすめの食べ物を紹介!

ビタミンの種類ごとに、それぞれの働きやおすすめの食べ物を詳しくご紹介していきます。
ビタミンA
ビタミンAは、皮膚の健康を保ち、のどや鼻などの粘膜に働いてウィルスが体内へ侵入するのを防いだり、暗いところでの視力を保ったりする働きがあります。
にんじんやほうれん草などの緑黄色野菜をはじめ、レバー、うなぎ、鶏卵、チーズなどの動物性食品にも多く含まれています。
ビタミンB1
ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変換する際に必要な栄養素。
皮膚や粘膜の健康を維持する働きもあります。
疲労回復や神経の働きを正常に保つのにも効果があるといわれています。
豚肉やうなぎ、豆類に多く含まれています。
ビタミンB2
ビタミンB2は、皮膚や髪の健康維持を助ける働きや、脂質を分解してエネルギーに変換する際に必要な栄養素。
レバーやうなぎ、納豆、乳製品などに多く含まれています。
ナイアシン(ビタミンB3)
ナイアシン(ビタミンB3)は、脂質やアミノ酸の代謝などをサポートする働きがあります。
酸化還元反応に関わる補酵素としての役割があります。
皮膚や粘膜の健康維持にも役立ちます。
玄米や鶏胸肉、かつおやマグロなどに多く含まれています。
パントテン酸(ビタミンB5)
パントテン酸(ビタミンB5)は、糖質、脂質、タンパク質の代謝とエネルギー産生に必要な酵素をサポートする働きがあります。
また、自律神経を正常に維持する役割もあります。
レバー、鶏胸肉、納豆、アボカド、さつまいもなどに多く含まれています。
ビタミンB6
ビタミンB6は、タンパク質の分解を助ける働きや、皮膚や髪の健康維持を助ける働きがあります。
かつおやマグロなどの魚類やバナナなどに多く含まれています。
ビタミンB6は腸内細菌によってもつくられます。
ビタミン12
ビタミンB12は、葉酸と一緒に赤血球中のヘモグロビンの生成を助ける働きをしています。
神経機能を正常に保つ役割もあります。
牡蠣やサンマ、あさりなどの魚介類や、レバーなどに含まれています。
葉酸
葉酸は、タンパク質や細胞を作るときに必要なDNAなどの核酸を合成する重要な働きがあります。
また、胎児の正常な発育に役立つため、妊娠前から葉酸摂取が推奨されています。
レバーや枝豆、ブロッコリー、とうもろこしなどに多く含まれています。
ビオチン
ビオチンは皮膚や髪の健康を保つ役割や、アミノ酸、脂質などのエネルギー代謝をサポートする働き、皮膚の炎症を抑える働きがあります。
レバー、卵、落花生、アーモンドなどに多く含まれています。
ビタミンC
ビタミンCはコラーゲンをつくるうえで必要な栄養素。
美肌効果や疲労回復効果、鉄の吸収を促進する働きがあります。
酸化を防いで老化や動脈硬化を予防します。
いちごやキウイフルーツ、アセロラ、ピーマン、ブロッコリーなどに多く含まれています。
ビタミンCの美肌効果については、こちらで詳しくご紹介していますので参考にしてください。
ビタミンD
ビタミンDはカルシウムの吸収を促進し、骨や歯の形成をサポートするはたらきがあります。
食品から摂取する以外にも、日光を浴びることで体内でも作り出すことができるビタミンです。
鮭やしらす干しなどの魚類や、きのこ類に多く含まれています。
ビタミンE
ビタミンEは強い抗酸化作用を持っていて、体内の脂質の酸化を防ぐ働きがあり、若返りのビタミンともよばれています。
アーモンドやオリーブオイル、いくらなどの魚卵、アボカドなどに多く含まれています。
ビタミンK
ビタミンKは、血液の凝固や骨の形成を促すなどの重要な働きがあり、腸内細菌によって体内でも合成されます。
小松菜やほうれん草などの緑黄色野菜や納豆などに多く含まれています。
こちらのコラムでも、美肌に欠かせない栄養素について詳しくご紹介していますので参考にしてください。
ビタミン不足を食べ物で効率良く解消するコツ
ビタミンを食事から効率良く摂取するポイントは、調理法にあります。
水溶性のビタミンであるビタミンB群とビタミンCは、水に溶けやすい性質があるため、調理方法によっては溶け出してしまったり、熱によって失われたりと、効率良く摂取できないケースがあります。
野菜は切ってから洗うとビタミンが流れ出てしまうので、切る前に洗い、長時間水にさらさないようにしましょう。
また、野菜は茹でると、茹で汁にビタミンが流出してしまうため、蒸したり、煮汁ごと飲めるスープなどにするのがおすすめです。
サラダやカットフルーツなど、生のまま食べられるものはそのまま食べて、ビタミンを効率良く摂取しましょう。
脂溶性のビタミンであるビタミンA・D・E・Kは、油と一緒に摂取することで体内に吸収されやすくなります。
油で炒める、揚げるなどの調理法がおすすめです。
サラダにするときは、オリーブオイルやマヨネーズなどのドレッシング類と一緒に食べると良いですよ。
ビタミン不足は食べ物で補う!調理方法も工夫しよう
ビタミンは体のエネルギー源となるタンパク質、糖質、脂質の代謝を助ける働きを持つ、健康を維持していくうえで大切な栄養素。
体内ではほとんど作ることができないため、普段の食事から摂取する必要があります。
無理なダイエットや偏った食生活などによって、ビタミン不足になる可能性も。
ビタミンが豊富な食材を毎日の食事に積極的に取り入れて、栄養バランスの良い食事を心がけることが大切です。
ビタミンは13種類あり、それぞれ役割も異なります。
水溶性ビタミン(ビタミンB群・ビタミンC)は、水に溶けやすい性質があるため、長時間水にさらさないように気をつけましょう。
野菜を茹でる際は、煮汁ごと飲めるスープなどにするのがおすすめです。
脂溶性のビタミン(ビタミンA・D・E・K)は、油で炒める、揚げるなどの調理法がおすすめ。
サラダにするときは、オリーブオイルやマヨネーズなどと一緒に食べましょう。
水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンの性質を生かした調理方法で、効率良くビタミンを摂取していきましょう。